煙草をワンカートン買ってネオン街を歩く2016年07月18日
◆晴れたり曇ったり。少し湿度が高かった一日。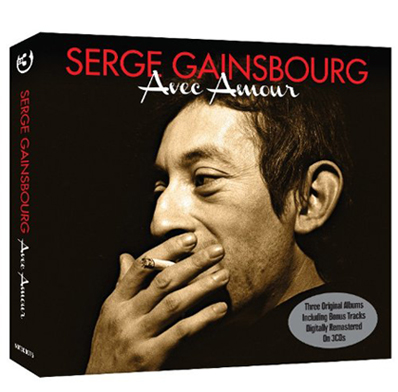
◆近所のコンビニがいつもの煙草を切らしてしまった(ちょっと発注ミスがあったような雰囲気)。あまり売っていない銘柄なので致し方なく確実に売っている札幌駅前のデパートまで買いに行って2カートンほど買ってきた(カートンとは煙草10個入りの箱だ)。カートンで買うなんて大人だね、と思われるかもしれないが、実は若い頃からカートンで買うことを覚えた。もう三十五年以上も前の出来事がきっかけだった。そのことを以前にエッセイで書いたので、その文章を多少改稿して以下に載せてみる。
◆初めて一人で夜の街に出たのは高校生の頃だ。僕が生まれた旭川市には三・六街という歓楽街がある。札幌のススキノを多少規模縮小したものだと思ってくれればいい。ネオンが輝くたくさんのビルに飲み屋が軒を並べ、普通の人たちもちょっと危ない人たちも、若者も年寄りも同じ道を歩き今夜の酒を楽しむ、そんな歓楽街だ。そこの一角にある菓子問屋でバイトを始めた。どうしてまたそんな、という経緯は話が長くなってそれで長編一本書けるので省くけれども、とにかく学校が終わってから僕はその歓楽街のど真ん中の小さな古い建物の菓子問屋に出勤して、飲み屋街を文字通り走り回ったんだ。仕事は、おつまみの配達。お菓子から珍味まで、バーやスナックといった飲み屋で出てくるようないわゆる〈乾きもの〉ならとにかく何でも扱っていた。
◆店から直接注文の電話を受けるとそれをメモして揃えて大きな布袋に入れて「行ってきます!」と、ネオン街に飛び出す毎日。何せ狭い範囲にごちゃっと店が固まった歓楽街だ。車や自転車などで配達していては駐車したりなんだりいちいち面倒で手間でしょうがない。だから、自分の足で走って届けるのがいちばん速かった。たくさんの人が行き交う歩道を軽やかにステップを踏んで、まるで障害物競走のように人々の合間を走り、路地をすり抜け、ビルの階段を昇って降りて、僕は〈おつまみ〉を配達していた。居酒屋、バー、スナック、クラブ、パブ、ストリップ劇場、ラーメン屋とありとあらゆる店に顔を出して「毎度様です!」と元気よく挨拶していた。当たり前の話だけど、いくら三十数年も前の時代とはいえ、普通の高校生がするようなアルバイトじゃなかった。だから、お店の人たちにとても珍しがられた。いつも声を掛けられた。
「高校生かよ? 偉いな坊主」
「あら、若いのに大変ねぇ。ご苦労様」
「無理すんなよ。明日も学校だろ?」
「気をつけろよ小僧。こういう場所はおっかねぇからな」
◆夜の街で働く人たちは皆、例外なく僕に優しかった。笑顔を向けてくれた。必ず十円と五円をお駄賃にくれた小料理屋のおかみさん、座ってジュースを飲んでいけと言ってくれるバーのマスター、焼きうどんを食べさせてくれた居酒屋の大将、いつか飲みに来たらタダにしてやると笑っていたパブの店長、高校生男子には目の毒なサービスをしていつもからかってくるストリッパーのお姉さん。そして、ドラマでしか聞かれないような、お約束みたいな言葉を本当に言ってくれたクラブのオーナーもいた。
「配達中に何かトラブルがあったら、俺の名前を出せ。それで片が付くから」
間違いなく怖い世界の住人であるその人は、見た目と裏腹に僕には優しかった。もし昼間にばったり会っても絶対に俺に声を掛けたり挨拶したりするな、と釘を刺してもくれた。普通の高校生である僕に迷惑が掛からないようにという配慮だったんだな、と気づいたのはしばらく経ってからだ。
◆バイトの最後の日、そのクラブのオーナーに「今日で終わりです」と言うと「学校も卒業か?」と訊いてきた。そうですと頷くと、にんまりと笑って言った。
「煙草は何を吸ってる」
「マルボロです」
「何だ随分といいもん吸ってやがんな」
その人は苦笑いしながら、マルボロをワンカートン買える金額を手渡してくれた。
「煙草をワンカートン、いつでも気軽に買える金を稼げる大人になれ。人生なんてそれで充分だ」
そう言って、この街を出ていっても頑張れよ、と、僕の背中をポンと叩いてくれた。
◆その言葉を、たぶんあの頃のあの人と同じような年齢になった今噛みしめる。本当に、人生はそれぐらいで充分だと思う。それぐらいの人生を送ることが実は本当に難しいのだと痛感する。
◆煙草のカートンを手にして街を歩くと、ふいにあの頃のことを思い出すこともある。
◆ネオンきらめく夜の街だ。たくさんの人々が舗道をそぞろ歩いていて、その騒めきが聞こえてくる。そういう夜のネオン街の光景を見ていると、その中に立つと、僕はたまらなくノスタルジーを感じる。懐かしくなる。もしくは〈青春〉という時代の真ん中にいた自分を思い出して、つい頬を緩めてしまう。あの頃に帰ってしまう。夜の街で働く人たちが、僕の中の一部分を作ってくれたと思っている。
◆感謝を込めて、街を歩く。